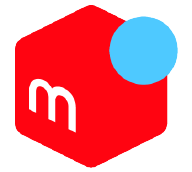ノンジアミンカラー徹底解説
2025/04/06
ノンジアミンカラー徹底解説
:アレルギーでも安心のヘアカラーで、髪と頭皮に優しい選択を
ノンジアミンカラーとは?
その成分、従来のヘアカラーとの違い
ノンジアミンカラーの定義と主要成分
ノンジアミンカラーは、ヘアカラーリング剤に含まれるジアミン、特にパラフェニレンジアミンという化学染料を一切使用していないヘアカラー剤のことです. ジアミンは、従来の酸化染毛剤において、効果的かつ鮮やかな発色を得るために不可欠な成分として広く用いられてきましたが、同時に、接触性皮膚炎やアレルギー反応を引き起こす主要な原因物質としても知られています。
ノンジアミンカラーの製品は多岐にわたり、その成分構成は一様ではありません。一般的には、ジアミンの代替として、植物由来の成分や天然染料、塩基性染料、HC(ヘアーコンディショニング)染料などが用いられています. 例えば、アミノ酸や植物エキスが配合されることで、髪のタンパク質の構成要素を補い、髪の健康を維持する役割や、髪に自然な艶を与えたり、水分を保持する効果が期待されています。
ただし、注意すべき点として、一部のノンジアミンカラー製品には、ジアミン以外の種類の酸化染料が含まれている可能性も否定できません. したがって、ヘアカラー後に何らかのアレルギー反応が現れた場合には、どの成分が原因となっているのかを特定するために、専門医の診断を受けることが重要です。
従来のヘアカラーにおけるジアミンの役割と懸念点
従来のヘアカラー、特に酸化染毛剤と呼ばれるタイプのヘアカラー剤において、ジアミン(パラフェニレンジアミン)は、その優れた染色力から主成分として利用されてきました。
ジアミンの特徴として、ごくわずかな量で濃く鮮やかな色を出すことができ、また、
複数の色を混ぜ合わせることで、幅広いカラーバリエーションを容易に実現できる点が挙げられます. これらの理由から、ジアミンは白髪染めやおしゃれ染めなど、多くのヘアカラー製品に不可欠な成分とされてきました。
特に、黒褐色のような濃い色味を表現するためには、ジアミンが現在最も効果的な染料であり、
アジア人の多くが求める自然な黒髪を染め上げるために重要な役割を果たしています。
しかしながら、ジアミンは強力な染色力を持つ一方で、人体に対してアレルギー反応を引き起こすリスクが非常に高いことが広く知られています。
ジアミンによるアレルギー症状は、頭皮のかゆみや赤み、かぶれ、発疹といった形で現れることが多く、重症化すると、顔全体や全身に症状が広がることもあります。
まれに、呼吸困難やアナフィラキシーショックといった深刻な症状を引き起こす可能性も指摘されています。
一度ジアミンアレルギーを発症してしまうと、その症状が完全に治癒することは難しいとされており、
繰り返しジアミンを含むヘアカラーを使用することで、症状が悪化したり、慢性化したりする危険性があります。
このような背景から、ヨーロッパの一部の国々では、ジアミンの使用が法的に禁止されていますが、
日本では現在も多くの白髪染め製品に配合されているのが現状です。
ノンジアミンカラーの染毛メカニズムの詳細
従来のジアミン系のヘアカラーは、アルカリ剤の作用によって髪のキューティクルを開き、染料の分子が髪の内部に浸透することで染色が行われます。
その後、酸化剤(通常は過酸化水素)との化学反応によって染料が発色・定着し、洗い流しても色が落ちにくいという特徴があります。
これに対し、ノンジアミンカラーの多くは、髪の表面に色素を吸着させることによって発色します。
例えば、塩基性染料を含むノンジアミンカラーは、プラスの電荷を持つ染料がマイナスの電荷を帯びた髪の表面にイオン結合することで色を定着させます。
また、HC染料は、分子が非常に小さいため、キューティクルのわずかな隙間から髪の内部に浸透しやすく、
比較的持ちの良い染色を可能にします。
HC染料は、ヘアマニキュアやカラートリートメントなどにも広く利用されています。
植物由来のノンジアミンカラー、特にヘナは、ヘナの葉に含まれるローソンという天然色素が、髪の主成分であるケラチンタンパク質に結合することで染色します。
このメカニズムにより、髪の表面をコーティングするだけでなく、髪にハリやコシを与える効果も期待できます。
さらに、古くから用いられているオハグロ式の白髪染め(現代ではマインドカラーなどが該当します)は、植物由来の染料と鉄剤を反応させることで、髪の内部から徐々に着色していくという特徴を持ちます。
この方法は、キューティクルへの負担が比較的少ないとされています。
成分、作用、仕上がりにおける従来のヘアカラーとの徹底比較
| 種類(一般名称) | 特徴 | 染料の種類(成分) | 染まり | 色持ち | ダメージ | ジアミンの有無 | 黒髪を明るくできるか | 白髪染めとしての適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸化染毛剤(ヘアカラー、ヘアダイ、おしゃれ染め、白髪染め) | 明るさや色味の調整が比較的自由。1剤と2液を混ぜるタイプ。 | 酸化染料(ジアミン含有) | ◎ | 1~2ヶ月 | 有 | 有 | 〇 | 〇 |
| 脱色剤(ブリーチ) | メラニン色素を分解して髪を明るくする。ジアミンは含まれない。 | 過硫酸塩など | × | - | 大 | 無 | 〇 | × |
| 半永久染毛料(ヘアマニキュア) | 髪の表面を酸性染料でコーティングする。脱色作用はない。 | 酸性染料 | 〇 | 約3週間 | ほぼ無 | 無 | × | △ |
| 半永久染毛料(カラートリートメント) | トリートメントベースにHC染料や塩基性染料を配合。髪の表面に色を付着させる。脱色作用はない。 | HC染料、塩基性染料 | △ | 約2~3週間 | ほぼ無 | 無 | × | △ |
| その他(ヘナ) | 植物由来の染料で、髪のタンパク質に結合して染まる。脱色作用はない。天然成分100%以外のものにはジアミンが含まれている可能性あり。 | 植物染料(ローソンなど)、一部ジアミン含有 | △ | 約3週間~1ヶ月 | ほぼ無 | 一部含有 | × | 〇 |
| ノンジアミンカラー(酸化染料) | ジアミンを使用しない酸化染料を用いたヘアカラー。製品によって明るくできるものもある。 | 酸化染料(ジアミンなし) | △ | △ | △ | 無 | △ | △ |
| 香草カラー | 製品によって成分が異なる。酸化染料を使用するものと、HC染料・植物染料を使用するノンジアミンタイプがある。 | 酸化染料またはHC染料・植物染料 | △~〇 | △~〇 | △~〇 | 製品による | × | △~〇 |
| ノンアルカリカラー | アルカリ剤を使用しないヘアカラー。ジアミンを含むものもある。 | 酸化染料(ジアミン含有) | △ | △ | 少 | 製品による | △ | △ |
| マインドカラー(非酸化染毛剤) | 天然植物性染料と鉄塩の化学反応で染毛する。脱色作用はない。 | タンニン酸硫酸鉄水和物 | 〇 | 約1ヶ月 | ほぼ無 | 無 | × | 〇 |
| リライズ(白髪染め) | 天然由来の黒髪メラニンのもと(ジヒドロキシインドール)で染める。脱色作用はない。 | ジヒドロキシインドール | △ | 約1ヶ月 | ほぼ無 | 無 | × | 〇 |
| ザクロペインター | ジアミンもアルカリ剤も使用しない白髪染め。ザクロ種子エキス配合。脱色作用はない。 | 塩基性アミノイオン水染料 | 〇 | △ | ほぼ無 | 無 | × | 〇 |
ノンジアミンカラーを選ぶメリット
ジアミンアレルギーを持つ人々への具体的な利点と科学的根拠
ノンジアミンカラーを選択する最大の利点は、何と言ってもジアミンアレルギーを持つ方が、
頭皮のかゆみや赤み、痛みといった不快な症状を心配することなく、安心してヘアカラーリングを楽しめるようになることです。
ジアミンアレルギーは、一度発症すると、その後のヘアカラーリングを困難にするだけでなく、日常生活においても様々な不便を強いられる可能性があります。
ノンジアミンカラーは、ジアミンを一切使用していないため、これらのアレルギー反応を引き起こすリスクを根本的に排除することができます. ジアミンアレルギーを持つ方に一般的に見られる症状
(頭皮のかぶれ、強いかゆみ、痛み、全身のだるさなど)を回避できることは、
単に美容上のメリットだけでなく、健康面における大きな利点と言えるでしょう。
さらに、現在ジアミンアレルギーの症状が出ていない方でも、ノンジアミンカラーを選ぶことで、
将来的にジアミンアレルギーを発症するリスクを低減できる可能性も示唆されています。
ジアミンは、繰り返し使用することで体内に蓄積され、ある閾値を超えるとアレルギー反応を引き起こすことがあるため、早期からノンジアミンカラーを選択することは、賢明な予防策となり得ます。
頭皮への優しさ:刺激の低減、敏感肌への適合性
ノンジアミンカラーは、ジアミンアレルギーの方だけでなく、頭皮が敏感な方にとっても多くのメリットがあります。
従来のヘアカラー剤と比較して、頭皮のかゆみや炎症を大幅に軽減できることが報告されています。
その理由の一つとして、多くのノンジアミンカラーは低アルカリ処方で作られている点が挙げられます。
アルカリ剤は、ヘアカラー剤が髪の内部に浸透するのを助ける役割がありますが、
同時に頭皮への刺激の原因となることもあります。
ノンジアミンカラーは、このアルカリ剤の配合量を通常よりも少なく抑えることで、頭皮への負担を最小限に抑えることを目指しています. また、従来のヘアカラー剤に特有の、ツンとした刺激臭の原因となるアンモニアの配合量も少ない傾向にあります。
これは、カラーリング中の不快感を軽減し、より快適な施術体験を提供します。
そのため、敏感肌の方でも、ノンジアミンカラーであれば比較的安心してヘアカラーリングを楽しむことができる場合が多いです。
ただし、注意点として、ノンジアミンカラーであっても、ジアミン以外の成分(例えば、アルカリ剤や過酸化水素など)に反応する可能性が皆無ではないため、敏感肌の方は特に、使用前に必ずパッチテストを行うことが推奨されます。
髪への優しさ:ダメージの軽減、保湿効果、質感への影響
ノンジアミンカラーは、頭皮への優しさだけでなく、髪への負担軽減にも配慮した製品が多く存在します。従来のヘアカラー剤と比較して、髪の毛の艶感を維持しやすいという特徴があります。
また、ノンジアミンカラーの中には、トリートメント成分を主体として配合しているものもあり、これらの製品を使用すると、カラーリング後の髪がしっとりとしなやかな質感に仕上がる傾向があります。
特に、植物由来の成分や天然成分を配合したノンジアミンカラーは、髪に潤いを与えたり、
水分を保持する効果が高く、カラーリングを繰り返すことで、髪の健康状態が改善されることも期待できます。
代表的な植物由来のノンジアミンカラーであるヘナカラーは、
髪の表面をコーティングするだけでなく、髪の内部にも浸透し、髪の主成分であるケラチンタンパク質と結合することで、髪にハリやコシ、そして自然なツヤを与える高いトリートメント効果を発揮します。
そのため、髪のダメージが気になる方や、髪のボリューム不足に悩んでいる方にとって、
ノンジアミンカラーは非常に魅力的な選択肢となります。
その他のメリット:臭いの少なさ、使用感など
ノンジアミンカラーは、従来のヘアカラー剤に比べて、カラーリング特有の刺激臭が少ないという点も大きなメリットとして挙げられます。
従来のカラー剤に含まれるアンモニアなどが原因となる不快な臭いが少ないため、カラーリング中の気分が悪くなりにくく、より快適な時間を過ごすことができます。
また、ノンジアミンカラーの中には、比較的暗めのトーンであれば、髪のメラニン色素を分解するブリーチ剤(過酸化水素)を使用せずにカラーリングできる製品もあります。
過酸化水素は、髪を明るくする効果がある一方で、頭皮への刺激や髪のダメージの原因となる可能性もあるため、
これを使用せずにカラーリングできることは、頭皮や髪への負担をさらに軽減する上で大きな利点となります。
さらに、ノンジアミンカラーの種類によっては、従来のジアミン入りのカラー剤よりも色持ちが良い場合や、
根元からしっかりと染めることができる製品も存在します。
これらのメリットは、より快適で、髪と頭皮に優しいカラーリング体験を求める多くの人々にとって、ノンジアミンカラーが魅力的な選択肢となる理由と言えるでしょう。
どのような人がノンジアミンカラーに適しているのか
ジアミンアレルギーの既往歴がある人
過去に従来のヘアカラーで頭皮にかぶれたり、強い痒みが出たり、顔が腫れてしまったりといったアレルギー反応を起こした経験のある方は、ノンジアミンカラーが最も適した選択肢となります。
特に、酸化染毛剤に含まれるジアミン系の染料(パラフェニレンジアミン、パラトルエンジアミン、ニトロパラフェニレンジアミンなど)にアレルギーを持つと診断された方は、必ずノンジアミンカラーを選ぶようにしてください。
一度ジアミンアレルギーを発症すると、繰り返しジアミンを含むヘアカラーを使用することで、
症状が悪化するリスクが高いため、安全性の高いノンジアミンカラーの使用が強く推奨されます。
頭皮が敏感で、従来のヘアカラーでトラブルを起こしやすい人
従来のヘアカラーを使用すると、カラーリング中に頭皮がピリピリしたり、ヒリヒリとした痛みを感じたり、強い痒みが生じたりする方は、頭皮が敏感である可能性が高く、ノンジアミンカラーを試してみる価値があります。
ノンジアミンカラーは、低アルカリ処方で刺激が少ないものが多いため、敏感な頭皮の方でも比較的安心して使用できる場合があります。
また、従来のヘアカラー特有のツンとした臭いが苦手な方にも、臭いの少ないノンジアミンカラーはおすすめです。
頭皮への刺激を最小限に抑えたいと考えている方にとって、ノンジアミンカラーは有効な選択肢となるでしょう。
髪のダメージを最小限に抑えたいと考える人
パーマやカラーリングを繰り返して髪が傷んでいる方や、もともと髪のダメージが気になっている方は、
ノンジアミンカラーの優しい成分が適しています。
ノンジアミンカラーの中には、髪の表面に色を吸着させるタイプのものが多く、
髪の内部への負担が少ない傾向があります。
また、ヘナカラーのように、染めながら髪にハリやコシ、ツヤを与えるトリートメント効果も期待できるノンジアミンカラーは、髪のダメージを補修しながらカラーリングを楽しみたい方におすすめです。
特定のヘアカラー製品や成分に懸念がある人
化学成分の使用をできるだけ避けたいと考えている方や、自然由来の成分にこだわったヘアカラーを選びたい方には、植物由来のノンジアミンカラー(ヘナカラーなど)が適しています。
これらの製品は、頭皮や髪への刺激が少なく、安心して使用できるというメリットがあります。
また、従来のヘアカラーに含まれるジアミン色素という成分に懸念がある方にとっても、ジアミンを一切使用していないノンジアミンカラーは、安心してカラーリングを楽しむための有効な選択肢となります。
具体的な事例を交えた解説
- 例1:ジアミンアレルギーがあり、長年ヘアカラーを諦めていたが、ノンジアミンカラーで再びカラーリングを楽しめるようになったケース :
- ジアミンアレルギーのために、これまでヘアカラーを諦めていた方が、
- ノンジアミンカラーを取り扱う美容院に出会い、事前のパッチテストで安全性を確認できたことで、再びおしゃれを楽しめるようになったという事例は多く報告されています。
- 例2:敏感肌で従来のヘアカラーで頭皮トラブルが頻発していたが、ノンジアミンカラーに変えたことで頭皮の悩みが解消されたケース :
- 敏感肌で、従来のヘアカラーを使用するたびに頭皮のかゆみや赤みに悩まされていた方が、
- ノンジアミンカラーに変えたところ、頭皮トラブルが劇的に改善され、安心してカラーリングを続けられるようになったというケースもあります。
- 例3:髪のダメージが気になり、ヘアカラーを控えていたが、トリートメント効果のあるノンジアミンカラー(ヘナなど)を試して髪質が改善されたケース :
- 髪のダメージが気になり、しばらくヘアカラーを控えていた方が、
- ヘナカラーのようなトリートメント効果の高いノンジアミンカラーを試した結果、白髪も自然に染まり、
- さらに髪にハリやコシが出て、以前よりも健康的な髪質になったという事例も少なくありません。
- 例4:妊娠中や授乳中で、刺激の少ないヘアカラーを探しているケース:
- 妊娠中や授乳中は、ホルモンバランスの変化などにより、肌がデリケートになっていることがあります。
- そのため、刺激の少ないヘアカラーを求める方もいますが、
- ノンジアミンカラーの中にも、念のためパッチテストを行うことが推奨される製品もあります。
- 使用する際は、必ず医師や美容師に相談し、安全性を確認することが重要です。
- 例5:おしゃれ染めを楽しみたいが、ジアミンアレルギーがあるため、明るく染められるノンジアミンカラーを探しているケース :
- ジアミンアレルギーがあるため、これまで暗めのカラーしか選べなかった方が、
- ノンジアミンカラーの中でも比較的明るい色味に対応している製品(例えば「ヘルバ」など)を取り扱っている美容院で、希望通りの明るい髪色に染めることができたというケースもあります。
現在市販されているノンジアミンカラーの種類とそれぞれの特徴
ヘナカラー:成分、特徴、メリット・デメリット、注意点
成分: ヘナカラーは、主にインドや北アフリカに自生する植物であるヘナの葉を乾燥させ、粉末にしたものが主成分です. ヘナの葉には、赤色色素であるローソンが含まれており、このローソンが髪のタンパク質であるケラチンと結合することで髪を染めます。天然成分100%のヘナ製品が一般的ですが、中にはより濃い色合いや染まりやすさを求めて、インディゴ(ナンバンアイ葉)などの他の植物成分や、
ごく稀にジアミンなどの化学染料が添加されている製品も存在するため、成分表示をしっかりと確認することが重要です。
インディゴを配合することで、ヘナ特有のオレンジがかった色味を抑え、ブラウン系の色合いに染めることが可能になります。
特徴: ヘナカラーは、髪の表面のタンパク質に結合して染まるため、髪の内部構造への影響が比較的少なく、脱色作用がないため、黒髪を明るく染めることはできません。
そのため、主に白髪染めとして利用されることが多いです。
ヘナの大きな特徴として、染めるたびに髪にハリ、コシ、ツヤを与える高いトリートメント効果が期待できる点が挙げられます。
また、ヘナは頭皮にも優しく、毛穴の余分な皮脂を取り除くことで、健やかな頭皮環境を保つ効果も期待できます。
メリット: ヘナカラーは、化学的な刺激が少ないため、髪や頭皮に穏やかに働きかけ、刺激やアレルギー反応のリスクを低減できます. 頭皮への負担も少なく、頭皮を保護し、健康的な状態を維持するのに役立ちます。
ジアミンなどのアレルギーを引き起こす成分が含まれていないため、皮膚が敏感な方やアレルギーのある方にも比較的安全に利用できます(ただし、植物アレルギーには注意が必要です) また、染め間隔をあまり気にする必要がなく、色を濃くしたい場合や染め直したい場合も、比較的短い間隔で使用できるとされています。
デメリット: ヘナカラーは、天然の染料であるため、色のバリエーションが限られ、主にオレンジや赤茶系といった暖色系の色味になります. また、染めるのに比較的時間がかかる場合があり , ヘナの収れん作用などにより、パーマがかかりにくくなる可能性も指摘されています。
黒髪を明るくすることができないため、おしゃれ染めにはあまり向きません。
100%ヘナとインディゴを使用して白髪をしっかり染めるには、二度染めが必要となる場合があり、
時間と費用がかかることがあります。
注意点: 天然成分100%を謳っていないヘナ製品の中には、染まりを良くするためにジアミンなどの化学染料が配合されている可能性があるため、購入前に成分表示を必ず確認しましょう。
植物アレルギーを持つ方は、ヘナに対してもアレルギー反応を示す可能性があるため、使用前に必ずパッチテストを行うようにしてください。
また、インディゴを使用した場合、後々化学染料によるヘアカラーチェンジが難しくなることがあるため、
注意が必要です。
カラートリートメント:成分、特徴、メリット・デメリット、注意点
成分: カラートリートメントは、トリートメントをベースに染料を配合したヘアカラー製品です。
主に、髪の表面に色を付着させるHC(ヘアーコンディショニング)染料や塩基性染料が用いられています。
また、多くのカラートリートメントには、髪のダメージを補修したり、潤いを与えるための様々な保湿成分や補修成分(例えば、ケラチン、コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド、ホホバオイル、アルガンオイルなど)が配合されています。
特徴: カラートリートメントの最大の特徴は、自宅で手軽に使用できる点です。
シャンプー後の濡れた髪に塗布し、数分置いて洗い流すだけで、徐々に髪に色を付けていくことができます。
また、髪へのダメージが非常に少ないことも魅力の一つです。
トリートメント成分が配合されているため、カラーリングと同時に髪のツヤ出し効果も期待できます。
一時的に色を付ける染料を使用しているため、もし仕上がりの色が気に入らなくても、シャンプーを繰り返すうちに自然に色が落ちていくという特徴もあります。
美容院で染めたヘアカラーの色持ちを長くキープするために使用する方もいます。
メリット: カラートリートメントは、通常のヘアカラーと比べて刺激が少ないため、デリケートな髪や頭皮の方でも比較的使いやすいとされています。
また、ジアミンフリーの製品がほとんどであるため、ジアミンアレルギーの方でも安心して使用できる場合が多いです。
カラーリング中に、従来のヘアカラーのようなツンとする嫌な臭いが少ないため、快適に使えるというメリットもあります. 白髪を目立たなくしたい、ヘアカラー後の色落ちを防ぎたい、あるいは一時的に髪色を変えて気分転換したいなど、様々な目的に合わせて選べる多様な製品が販売されています。
デメリット: カラートリートメントは、髪の表面に色を付着させる仕組みであるため、一度の使用ではなかなか色が定着しにくいというデメリットがあります。
しっかりと色を入れたい場合は、数日間連続で使用する必要があることが多いです。
また、色持ちは一般的に2〜3週間程度と、通常のヘアカラーに比べて短めです。
メラニン色素を分解する脱色効果はないため、髪を明るくすることはできず、黒髪に使用しても色の変化はわずかです。
染めた直後は色落ちしやすく、タオルなどに色が付着することがあるため注意が必要です。
カラートリートメントを使用している髪に、後日、酸化染毛剤やヘアマニキュアなどの他のヘアカラーを施すと、予期せぬ色の変化やムラが生じる可能性があるため、注意が必要です。
注意点: 白髪をしっかりと染めたいという方には、カラートリートメントよりもヘアカラー(酸化染毛剤)の使用が推奨されます. 汗や雨などで色落ちしやすい傾向があるため、特に夏場や運動後などは注意が必要です. 染める前の髪色や髪質によって、仕上がりの色合いが異なってくる場合があることも理解しておきましょう。
その他のノンジアミンカラー製品(例:香草カラー、マインドカラー、リライズなど):成分、特徴、メリット・デメリット、注意点
-
香草カラー: 「香草カラー色葉」は、酸化染料を一切使用せず、天然植物(ナンバンアイ・ヘナ)の染料とHC染料を組み合わせたノンジアミンコスメカラーです. ジアミンアレルギーの方でも使用でき , 髪や頭皮に負担をかけずに、ハリ・コシ・ツヤのある健康的な髪を保つ効果が期待できます. 明るくすることはできませんが、白髪を染めたい方におすすめです。 ただし、「香草カラーMD」「香草カラーLU」「香草カラーGREY」はノンジアミンではないため、注意が必要です。
-
-
マインドカラー (非酸化染毛剤): 酸化染料(ジアミン等)と酸化剤(過酸化水素)を使用せず、天然植物性染料(ポリフェノール類等)と鉄塩の化学反応で染毛する非酸化染毛剤です. オハグロ式ヘアカラーの一種で , ジアミン系染料が無配合のため、ジアミンアレルギーの方でも使用できます. ツンとする刺激臭がなく , 色持ちは約1ヶ月程度とされています。
-
脱色効果はないため、黒髪を明るくすることはできず、黒または黒に近い色にしか染まりません。
-
パーマがかかりにくくなることがある点や、1剤と2剤を時間差で使用するため、染毛操作がやや面倒である点がデメリットとして挙げられます。
-
-
リライズ (白髪染め):
-
100%天然由来の黒髪メラニンのもと(ジヒドロキシインドール)だけで染める次世代型白髪ケア製品です。使うたびに白髪に自然な黒さを補い、繰り返し使っても髪を傷めず、ハリ・コシ・自然なツヤを与えます。
-
お風呂で使えて、5分放置したら洗い流すだけの簡単さが特徴で、ニオイも気にならない無香性です. 脱色の働きはないため、髪を明るくすることはできず、黒または黒に近い色にしか染まりません. 色持ちはジアミンを使用した酸化染毛剤よりも短く、1ヶ月程度です。
-
ザクロペインター:
-
ジアミンもアルカリ剤も使用していない最新の白髪染めです。
-
地毛の黒髪は明るくできませんが、白髪にはしっかりと色が乗り、ザクロ種子エキス配合により、頭皮や髪に良い効果が期待されています。
-
施術中や施術後の刺激や痒みが少ないのが特徴で、数種類の色味を混ぜて調合することも可能です。
-
ただし、通常のカラーよりも色落ちがしやすい傾向があるため、専用シャンプーの使用が推奨されています。
-
| 製品名(俗称) | 染料の種類(成分) | 染まり | 色流れ | 色持ち | 黒髪を明るくできるか | 白髪染めとしての適性 | アレルギーリスク | 髪・頭皮への負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンジアミンカラー(酸化染料) | 酸化染料(ジアミンなし) | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 低 | △ |
| ヘナインディゴ | 植物染料(ローソン、インディゴ) | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 低(植物アレルギーに注意) | 低 |
| ヘアマニキュア | 酸性染料 | 〇 | × | △ | × | △ | 低 | 低 |
| ポリサージュ | グロス染料 | △ | △ | × | × | × | 不明 | 不明 |
| 利尻昆布 | ニトロ染料、HC染料、塩基性染料 | △ | × | × | × | △ | 低 | 低 |
| マインドカラー(非酸化染毛剤) | タンニン酸硫酸鉄水和物 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 低 | 低 |
| リライズ(白髪染め) | ジヒドロキシインドール | △ | 〇 | △ | × | 〇 | 低 | 低 |
| CTFカラー | 不明 | △ | × | × | △ | △ | 不明 | 不明 |
| ノンジアミンヘルバ(酸化染料) | 酸化染料(ジアミンなし) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 低 | △ |
| 香草カラー色葉 | HC染料、植物染料(ナンバンアイ、ヘナ) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 低(植物アレルギーに注意) | 低 |
| ザクロペインター | 塩基性アミノイオン水染料、ザクロ種子エキス | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 低 | 低 |
ノンジアミンカラーの一般的な使用方法、注意点、染め方のコツ
使用前の準備:パッチテストの重要性と実施方法
ノンジアミンカラーは、ジアミンを含まないため、ジアミンアレルギーの方でも比較的安心して使用できるとされていますが、全ての方にアレルギー反応や皮膚刺激が起こらないわけではありません。
ジアミン以外の成分、例えば、製品に含まれる他の染料や植物エキス、防腐剤、香料などによってアレルギー反応を引き起こす可能性も否定できません. そのため、ノンジアミンカラーを使用する前にも、必ずパッチテストを行うことが非常に重要です。
パッチテストは、製品を使用する48時間前(または製品によっては24時間前)に行うことが推奨されています。
具体的な手順としては、まず、腕の内側など目立たない場所に、清潔にした皮膚に少量のカラー剤を塗布します。
その後、自然乾燥させ、指定された時間(通常は48時間)そのまま様子を見ます。
この間、塗布部位をガーゼなどで覆ったり、洗い流したりしないように注意してください。
もし、塗布部位に炎症、かゆみ、赤み、発疹などの異常が見られた場合は、その製品の使用を直ちに中止し、皮膚科専門医の診察を受けるようにしてください。
過去にヘアカラーで何らかのアレルギー症状が出たことがある方はもちろん、初めてノンジアミンカラーを使用する場合でも、必ずパッチテストを実施して、ご自身の肌に合うかどうかを確認することが大切です。
基本的な染め方:塗布の手順、放置時間、洗い流し方
ノンジアミンカラーの基本的な染め方は、製品の種類によって異なる場合がありますので、使用する前に必ず製品に付属の取扱説明書をよく読み、その指示に従って正しく使用してください。
一般的な手順としては、まず、染める前に髪を丁寧に洗い、余分な汚れやスタイリング剤をしっかりと落としておくことが推奨されます. 清潔な髪は、染料の浸透を助け、ムラなく染め上げるために重要です。
次に、染料を髪の根元から毛先まで、均一に塗布していきます. 白髪が気になる部分や、特にしっかりと染めたい部分には、やや多めに染料を使用すると良いでしょう。
製品によっては、塗布する範囲やデザインを事前に決めておくと、よりスムーズに作業を進めることができます. 染料が衣服や皮膚に付着するのを防ぐために、使い古したタオルを肩にかけたり、付属の手袋を着用したりするなどの対策をしっかりと行いましょう。
染料を塗布したら、製品ごとに指定された放置時間を守って待ちます。
ノンジアミンカラーの中には、比較的長めに放置しても、色が濃くなりすぎない特性を持つものもあるため、
製品の説明書をよく確認してください. 放置時間が終了したら、ぬるま湯で丁寧に染料を洗い流します。
その後、必要に応じてシャンプーやトリートメントを使用し、髪を整えてください。
ヘアマニキュアタイプのノンジアミンカラーは、頭皮に付着すると色が落ちにくい場合があるため、根元から少し離して塗布する必要があることがあります。
製品によっては、専用のブラシが付属しており、それを使って髪をとかすようにして染めていくタイプもあります。
使用上の注意点:色移り、頭皮への刺激、アレルギー反応など
ノンジアミンカラーを使用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、染めたての髪は、数日間程度色落ちしやすい傾向があるため、特に色の薄いタオルや寝具への色移りに注意が必要です。
洗髪後や就寝時には、色の濃いタオルを使用したり、枕にタオルを敷いたりするなどの対策を講じると良いでしょう。
特に初めて使用する製品の場合は、念入りに色移り対策を行うことが推奨されます。
また、ノンジアミンカラーはジアミンを含まないものの、他の成分によって頭皮に刺激を感じたり、まれにかぶれやかゆみが生じたりする可能性もゼロではありません。
使用中に、あるいは使用後に、頭皮や髪に何らかの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医に相談することが重要です。
市販されているノンジアミンカラーは、美容院で使用されるものと比較して、濃い色や深みのある色を出すのが難しい場合や、明るくする作用がない製品が多いことを理解しておく必要があります。
また、普段から他のヘアカラー剤を使用している場合は、ノンジアミンカラーとの相性によっては、期待通りの染め上がりにならない可能性もあるため、注意が必要です。
きれいに染めるためのコツ:塗布量の調整、放置時間の管理、アフターケア
ノンジアミンカラーで髪をきれいに染めるためには、いくつかのコツがあります。
まず、染料はケチらず、髪全体にたっぷりと、ムラのないように塗布することが重要です。
特に白髪が多い部分や、しっかりと染めたい部分には、念入りに塗布しましょう。
次に、製品ごとに指定された放置時間をきちんと守ることが大切です。
ノンジアミンカラーの中には、放置時間をやや長めに設定することで、よりしっかりと染まるものもありますが、製品の説明書をよく確認してください。
製品によっては、放置中に加温することで染まりが良くなる場合もあります。
もし、一度のカラーリングで満足のいく色に染まらなかった場合は、間隔を空けずに数日連続で染め直すと、
より色が定着しやすくなります。
染めた後のアフターケアも、色持ちを良くするために非常に重要です。
カラーリング後24〜48時間は、できるだけシャンプーを避けることで、色素が髪にしっかりと定着しやすくなります。
その後のシャンプーは、カラーヘア専用のシャンプーやトリートメントを使用することで、色落ちを抑え、髪のダメージをケアすることができます. 洗髪の頻度を減らすことや、
ドライヤーの熱や紫外線から髪を守ることも、色持ちを良くする上で有効です。
また、ノンジアミンカラーの種類によっては、カラートリートメントを併用することで、
色のバリエーションを増やしたり、色持ちを向上させたりすることができる場合があります。
美容院でノンジアミンカラーの施術を受ける場合は、事前に希望する色味や髪の状態を美容師に詳しく伝え、
カウンセリングをしっかりと行うことが、理想の仕上がりを実現するための重要なポイントとなります。
ノンジアミンカラーに関する最新のニュース、トレンド、専門家の意見
ノンジアミンカラー市場の最新動向とトレンド
近年、ヘアケアに対する消費者の関心が高まっており、「人にも髪にも環境にも優しい」製品が求められる傾向が強まっています。
このような背景から、頭皮への刺激やアレルギーのリスクが低いノンジアミンカラーの需要が急速に増加しています。
ジアミンアレルギーを持つ人の割合が増加傾向にあることも、ノンジアミンカラーへの関心を高める要因の一つと考えられます。
従来のノンジアミンカラーは、色の表現力、特に明るい色味やアッシュ系のニュアンスを出すのが難しいとされていましたが、近年では、これらの課題を克服した製品が登場しています。
例えば、「アペティート ノンジアミン ヘルバ」は、ジアミンフリーでありながら、明るい色味や透明感のある発色を実現できるとして注目されています。
また、環境ホルモンを含まないノンジアミンカラーなど、より安全性を追求した製品開発も進んでいます。
さらに、米粉を主成分としたノンジアミンカラーなど、新しい原料を使用した製品も登場しており、
今後の展開が期待されます。
美容業界におけるノンジアミンカラーの最新情報
美容業界においても、ノンジアミンカラーへの注目度は高まっており、多くの美容院がノンジアミンカラーの施術メニューを取り入れるようになっています。
美容師向けのノンジアミンカラーに関する情報発信も活発に行われており、施術技術の向上や、カラートリートメントとの組み合わせによる新たな色表現の探求など、様々な取り組みが行われています。
これは、ノンジアミンカラーが、単にアレルギーを持つ方への代替手段としてだけでなく、髪と頭皮に優しいカラーリングの選択肢として、広く認知され始めていることを示唆しています。
皮膚科医や毛髪専門家によるノンジアミンカラーに関する意見やアドバイス
皮膚科医や毛髪専門家の間では、ジアミンアレルギーを持つ方にとって、ノンジアミンカラーは安全性の高い選択肢として推奨されています。
ただし、ノンジアミンカラーであっても、全ての方にアレルギー反応が起こらないわけではないため、使用前のパッチテストは必ず行うべきであるという意見で一致しています。
ジアミン以外の成分によるアレルギーの可能性も考慮する必要があるため、過去に他の化粧品や植物などでアレルギーを起こした経験のある方は、特に注意が必要です。
頭皮や髪の健康を重視する方にとって、ノンジアミンカラーは有効な選択肢となり得ますが、
製品の特性をしっかりと理解し、自身の髪質や希望する仕上がりに合わせて適切な製品を選ぶことが
重要であると専門家は指摘しています。
まとめ
ノンジアミンカラーは、従来のヘアカラーに含まれるジアミンというアレルギーを引き起こす可能性のある化学染料を一切使用していない、髪と頭皮に優しいヘアカラーリングの選択肢です。
特に、ジアミンアレルギーを持つ方にとっては、安心してヘアカラーを楽しむための重要な手段となります。
従来のヘアカラーと比較して、アレルギーのリスクや頭皮への刺激が少ないという大きなメリットがある一方で、
製品によっては色持ちや色の表現力に限りがある場合もあります。
しかしながら、近年ではノンジアミンカラーの技術も進歩しており、様々な種類の製品が開発・販売されています。
植物由来のヘナカラーや、自宅で手軽に使えるカラートリートメント、
そして美容院で施術を受けることができる最新のノンジアミンカラーなど、選択肢は多岐にわたります。
名古屋市内においても、ノンジアミンカラーを取り扱う美容院が増えております。
ノンジアミンカラーを選ぶ際には、ご自身の髪質やアレルギーの有無、そして希望する仕上がりのイメージに合わせて、最適な製品や施術方法を選ぶことが大切です。
使用前には必ずパッチテストを行い、製品の取扱説明書をよく読んで正しく使用することで、
より安全で快適なノンジアミンカラー体験を楽しむことができるでしょう。
最新のトレンドや専門家の意見も参考にしながら、髪と頭皮に優しいノンジアミンカラーを賢く活用し、
より豊かなヘアカラーライフを送ってください。
----------------------------------------------------------------------
リリー美容室
〒462-0051
愛知県名古屋市北区中切町3-1-1
電話番号 : 052-915-8222
北区でカラーとケアをするなら
----------------------------------------------------------------------